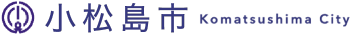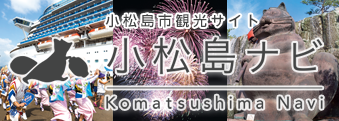養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんが、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。
受給手続きについて
申請に必要な下記の1から6の書類をそろえて、小松島市役所保険年金課(1階4番窓口)に提出し、医療券の交付を受けて指定医療機関で医療の給付を受けてください。(※書類がそろい次第、早めに申請してください。)
- 申請書 (PDF 70.6KB)(保護者が記入してください)※記入のしかた (PDF 108KB)
- 世帯調書 (PDF 57.7KB)(保護者が生計を一にする家族について記入してください)※記入のしかた (PDF 95.4KB)
- 意見書 (PDF 84.2KB)(主治医に記入してもらってください)
- お子様の保険証(コピー可)
- 認印
- 家族全員(子どもをのぞく)の所得税を確認する書類(詳細は下記の「所得税額確認書類一覧」及び注意事項をご確認ください。)
| 所得税等の状況 | 提出する書類 | 発行先 | |
|---|---|---|---|
| 自分で事業をしている方 | 確定申告書の控え(税務署等の受付印のあるもの) もしくは納税証明書(種類「その1」、税目「申告所得税」) |
税務署 | |
| 会社等に勤務し、給与支払を受けている方 | 給与所得だけの場合 (確定申告なし) |
源泉徴収票 | 勤務先 |
| 給与所得だけの場合 (確定申告有り) |
確定申告書の控え(税務署等の受付印のあるもの) もしくは納税証明書(種類「その1」、税目「申告所得税」) ※源泉徴収票を確定申告で提出している場合は証明を受けようとする事項「源泉徴収税額」にチェックをいれてください。 |
税務署 | |
| 給与所得と事業所得の両方がある場合 | |||
| 生活保護を受けている方 | 生活保護受給証明書 | 生活福祉課 | |
| 上記証明書のとれない方 | 市区町村民税の課税(非課税)証明書 | 該当年の1月1日に住所があった市区町村 | |
※注意事項
源泉徴収票または確定申告書において所得税額が0円である場合には、そのほかに、市区町村民税課税(非課税)証明書の提出が必要です。
源泉徴収票又は確定申告書(納税証明書)の場合
- 1月から6月に申請する場合=前々年分の証明書類
- 7月から12月に申請する場合=前年分の証明書類
市区町村民税課税(非課税)証明書の場合
- 4月から6月に申請する場合=前年度の証明
- 左記以外の時期に申請する場合=当該年度の証明
- 小松島市で市区町村民税の課税状況の確認できる方は市区町村民税課税(非課税)証明書の添付の省略可。
- なお、源泉徴収票等において扶養家族として確認できる方の証明書は不要です。
※下記【マイナンバー制度の開始にあたって】もご覧ください。
公費負担の範囲及び自己負担金等について
養育医療にかかる入院治療費で、健康保険適用後の自己負担額を公費負担します。世帯の所得税額に応じて一部自己負担金が必要ですが、これについては子どもはぐくみ医療費助成事業で公費負担となりますので、必ず、子どもはぐくみ医療費助成の申請も合わせて行ってください。(※養育医療にかかる医療費については、窓口での負担はありません。ただし、おむつ代や差額室料、文書料等保険が適用されないものは給付対象外ですので直接、病院へお支払いいただくようになります。)
医療券の発行ついて
申請書を提出してから約1週間から2週間くらいで自宅に医療券を郵送します。病院への支払い時は、養育医療の申請中であることを申し出て、支払金額については病院の説明を十分お聞きください。(※この制度は医療費を支給するものではなく、医療そのものを給付するものです。従って、既に医療費を支払った場合、払い戻しはできませんのでご注意ください。)
マイナンバー制度の開始にあたって
マイナンバー制度の開始により、申請等の様式には個人番号(マイナンバー)記入欄が設けられています。個人番号の記入にあたっては、本人確認のため、次のものを提示していただく必要があります。
保護者(健康保険の被保険者等)ご自身が手続きをする場合
- 保護者の方の『個人番号カード』または『住民票に記載されている事項と一致している通知カードと顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』または『住民票に記載されている事項と一致している通知カードと顔写真のない本人確認書類(健康保険の被保険者証、年金手帳等)2点』または『個人番号が記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)と顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』
- お子様の『個人番号カード』または『住民票に記載されている事項と一致している通知カード』(写しでも可)
- お子様と同一世帯の家族全員およびそれ以外でお子様を扶養している扶養義務者の『個人番号カード』または『住民票に記載されている事項と一致している通知カード』(写しでも可)『委任状』または『官公署等が発行した書類(健康保険の被保険者証等)』
保護者(健康保険の被保険者等)以外の方が手続きをする場合
- 法定代理人(成年後見人等)の場合は、『戸籍謄本その他その資格を証明する書類』または『保護者について官公署等が発行した書類(健康保険の被保険者証等)』
- 手続きをする方の『顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)1点』または『顔写真のない本人確認書類(健康保険の被保険者証、年金手帳等)2点』
- 保護者、扶養義務者およびお子様の『個人番号カード』または『住民票に記載されている事項と一致している通知カード』または『個人番号が記載された住民票の写し(もしくは住民票記載事項証明書)』(写しでも可)『委任状』または『官公署等が発行した書類(健康保険の被保険者証等)』
※扶養義務者とは…父、母、祖父母、養父母、兄弟姉妹、その他家庭裁判所で扶養の義務が負わされた叔父叔母等