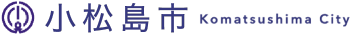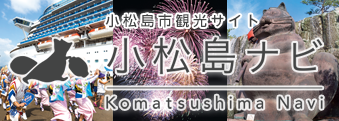国民健康保険税について
1 令和6年度国民健康保険税の税率
「徳島県国民健康保険運営方針」の見直しにより、保険税算定方式の一つである「資産割」の段階的な縮小・廃止が示されました。この方針を受け、本市でも令和5年度に「資産割」を廃止しております。
令和6年度の保険税率は令和5年度と同率です。
| 区分 | 令和4年度税率 | 令和5年度税率 |
令和6年度税率 (改正なし) |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
基礎課税額(医療分) |
被保険者の所得(注1)に応じて計算 | 所得割率 | 8.6% | 9.0% | 9.0% |
| 被保険者の資産(注2)に応じて計算 | 資産割率 | 11.2% | (廃止)0% | (廃止) | |
| 世帯の被保険者数に応じて計算 | 均等割額 | 24,500円 | 26,000円 | 26,000円 | |
| 世帯につき計算 | 平等割額 | 24,800円 | 24,800円 | 24,800円 | |
|
後期高齢者支援金等課税額 |
被保険者の所得(注1)に応じて計算 | 所得割率 | 2.4% | 3.0% | 3.0% |
| 被保険者の資産(注2)に応じて計算 | 資産割率 | 2.75% | (廃止)0% | (廃止) | |
| 世帯の被保険者者数に応じて計算 | 均等割額 | 6,800円 | 8,000円 | 8,000円 | |
| 世帯につき計算 | 平等割額 | 6,800円 | 6,800円 | 6,800円 | |
|
介護納付金課税額 |
被保険者の所得(注1)に応じて計算 | 所得割率 | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
| 被保険者の資産(注2)に応じて計算 | 資産割率 | 2.45% | (廃止)0% | (廃止) | |
| 世帯の被保険者数に応じて計算 | 均等割額 | 9,000円 | 10,500円 | 10,500円 | |
| 世帯につき計算 | 平等割額 | 5,900円 | 5,900円 | 5,900円 | |
国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の合計です。上記の税率に基づき世帯単位で計算します。
基礎課税額分(医療分)・・・・医療費を支払うために負担していただく分
後期高齢者支援金等課税額分・・後期高齢者医療制度を支えるために負担していただく分
介護納付金課税額分・・・・・・介護保険の財源にあてるために負担していただく分
(注1)所得とは、被保険者の前年中の総所得金額及び山林所得金額並びにその他の所得と区分して計算される所得の合計金額から基礎控除43万円を差し引いた金額です。
(注2)資産とは、被保険者の土地及び家屋の固定資産税額です。
2 国民健康保険税の軽減制度
一定の所得以下の世帯については、「均等割」と「平等割」が軽減されます。令和6年度に改正された軽減判定基準は次のとおりです。
| 軽減割合 | 世帯主とその世帯の被保険者(特定同一世帯所属者を含む)の所得の合計額 |
|---|---|
| 7割 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)以下 |
| 5割 | 基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)以下 |
| 2割 | 基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)以下 |
世帯主は国民健康保険被保険者でない場合も含みます。
特定同一世帯所属者とは、同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者に移行された方で、以後その世帯に継続して所属している方です。
(注1)給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受ける方
年度途中で異動があった世帯の軽減判定について
年度途中に被保険者が異動しても4月1日現在を基準として判定します。ただし、世帯主の異動があった場合(新規加入・世帯主変更・世帯合併・世帯分離など)については、その月を基準として判定をします。
3 未就学児の「均等割」軽減制度
令和4年度から未就学児の均等割額について5割軽減します。なお、一定所得以下の世帯を対象とする軽減制度(上記「2国民健康保険税の軽減制度」参照)に該当する世帯の未就学児については、軽減後の均等割額をさらに5割減額します。
申請は不要で、自動的に減額されます。
4 産前産後相当期間の軽減制度
国民健康保険に加入されている方が出産される場合、産前産後相当期間の国民健康保険税が軽減される制度です。(※申請が必要です)
詳しくはこちらをご覧ください。産前産後相当期間の国民健康保険税の軽減について
5 後期高齢者医療制度移行に伴う軽減制度
国民健康保険被保険者から後期高齢者医療制度への移行に伴う軽減制度
【特定世帯】
特定世帯とは、国民健康保険被保険者から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯で、かつ国民健康保険の被保険者が1名となった世帯については、その世帯に異動がない限り5年間基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の平等割額を半額に減額します。
【特定継続世帯】
特定継続世帯とは、国民健康保険被保険者から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯で、かつ国民健康保険の被保険者が1名となった世帯であり、特定世帯の減額期間を満了した世帯です。その世帯に異動がない限りその後3年間、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額の平等割額を4分の1減額します。
なお、「特定世帯」「特定継続世帯」が、上記2の軽減制度の対象世帯である場合は、半額もしくは4分の1減額後の平等割額をさらに7割・5割・2割の各割合で軽減します。
被用者保険の被扶養者であった方(旧被扶養者)に対する減免制度
被用者保険の被用者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴って、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者といいます。)については、申請により国民健康保険税の減免制度が適用されます。所得割額、資産割額は期間の定めなく全額免除され、均等割額が資格取得日の属する月から2年間半額免除となります。また、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平等割額も資格取得日の属する月から2年間半額免除されます。なお、上記2の軽減制度「7割軽減」「5割軽減」の対象となる世帯は除きます。
6 特例対象被保険者等(非自発的失業者)の国民健康保険税軽減制度
対象となる方
次の1.2.3すべてに該当する方が対象となります。
- 65歳未満で離職した方
- 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者として失業等給付を受ける方
- 雇用保険受給資格者証等の第1面「離職理由」欄の番号が11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方
軽減額
対象となる方の前年の給与所得を30/100として国民健康保険税の算定をします。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
申告に必要なもの(必ず申告が必要です。)
- 国民健康保険証
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
7 国民健康保険税はいつから納めるの?
国民健康保険税は被保険者の資格が発生したときから計算され、市役所窓口で届出をしたときからではありません。届出が遅れると資格が発生した月にさかのぼって国民健康保険税を負担することになります。
8 国民健康保険税の納め方
納付の責任は世帯主!
国民健康保険税は被保険者一人ひとりが個別に納めるのではなく、世帯ごとにまとめて世帯主が納めます。
家族の中に被保険者がいる場合は、世帯主は国民健康保険に加入していなくても、国民健康保険税の納税義務者となります。
国民健康保険税は、特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書での納付または口座振替による納付)の2種類の納め方があります。
特別徴収(年金天引き)
対象者 |
特別徴収は、世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主であって、年金額が年間18万円以上の方が対象となります。(年度途中で75歳になる方を除く)。ただし、年金天引きされる介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金額の1/2を超える場合は、介護保険料のみ年金天引きとなり、国民健康保険税は普通徴収となります。 |
|---|---|
納付時期 |
特別徴収(年金天引き)は、年6回(年金支給月である4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)で、国民健康保険税が年金から天引きされます。 |
納付内容 |
特別徴収は毎年度4月から始まりますが、4月・6月・8月の3回は前年度の2月分の特別徴収額と同額となります(仮徴収)。 また、10月・12月・翌年2月の3回は、当該年度分の国民健康保険税額(7月に決定)から仮徴収額を差し引いた額を天引きします(本徴収)。 |
普通徴収(納付書または口座振替での納付)
対象者 |
普通徴収は、特別徴収以外の方が対象となります。なお、年度途中に65歳または75歳になる方や市外から転入した方等は、年金の有無にかかわりなく、一時普通徴収となります。 |
|---|---|
納付時期 |
普通徴収は、年8回(1期(7月)・2期(8月)・3期(9月)・4期(10月)・5期(11月)・6期(12月)・7期(翌年1月)・8期(翌年2月))となります。 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別徴収 | ● 仮徴収 |
● 仮徴収 |
● 仮徴収 |
● 本徴収 |
● 本徴収 |
● 本徴収 |
||||||
| 普通徴収 | ■ 1期 |
■ 2期 |
■ 3期 |
■ 4期 |
■ 5期 |
■ 6期 |
■ 7期 |
■ 8期 |
9 国民健康保険税のお支払い方法が変更できます。(申請が必要です。)
特別徴収(年金天引き)対象の方は、申請により、お支払い方法を口座振替に変更することができます。口座振替でのお支払いを希望される方は、市税務課へのお申し出が必要です。
10 国民健康保険税の納税通知書等の送付時期
各年度分(4月から3月まで)の国民健康保険税については、納付方法(特別徴収、普通徴収)に関係なく、毎年7月に納税通知書、特別徴収通知書等をお送りします。
国民健康保険税は被保険者の資格が発生した月から必要です。年度途中に資格が発生した場合は月割で計算します。
4月から6月中旬の間に被保険者の資格が発生した場合、当該年度分の国民健康保険税は、7月に納税通知書等をお送りします。
それ以降に被保険者の資格が発生した場合、当該年度分の国民健康保険税は、原則として翌月に納税通知書等をお送りします。