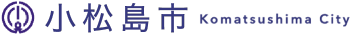食品ロスとは
まだ食べられるのに廃棄されている食品を「食品ロス」といいます。
日本における食品ロスの年間発生量は、約643万トンと推計されており(平成28年度農林水産省及び環境省推計)、国民一人当たりに換算すると、お茶碗一杯分の食品が毎日ごみとして廃棄されています。
食品ロス削減の取り組み
◇賞味期限を正しく理解する
食品の期限表示には、賞味期限と消費期限の2種類があります。
賞味期限は「おいしく食べることができる期限」、消費期限は「安全に食べることができる期限」です。
廃棄前に、ご確認ください。ただし、記載の期限は、「開封前の期限」ですので、開封後は早めに食べるよう心がけましょう。
◇食材は必要な時に、必要なだけ購入する
買い物に行くときは、冷蔵庫の中を確認し、必要な分だけ買うように心がければ、食品ロスの削減につながります。
◇余った食材を活用する
茎や皮に多くの栄養が含まれる野菜もあります。今まで廃棄していた野菜の茎や皮などを使って料理したり、残りものを他の料理に作り替えるなど、献立や調理方法を工夫しましょう。
◇食べ残しをしない
外食のときは、料理の量が多いときは少なめにできるか、食べられない食材を抜くことができるかなどを確認し、食べ残しをしないよう心がけましょう。
◇3010運動に取り組みましょう
「3010(サンマルイチマル)運動」とは、食品ロス削減のための運動で「宴会開始から30分間と、宴会終了10分前は、座席で食事を楽しみましょう」というものです。この取り組みは長野県松本市で2011年に始まり、全国に広がりつつあります。
全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会
平成28年10月、食品ロスの削減などを目的に「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」が設立されました。
この協議会には「おいしい食べ物を適量で残さず食べきる運動」の趣旨に賛同する地方公共団体が参加しており、食品ロスについての啓発活動や関係団体への要請活動などを行っています。
本市も、この協議会に参加しており、食品ロス削減を推進しています。